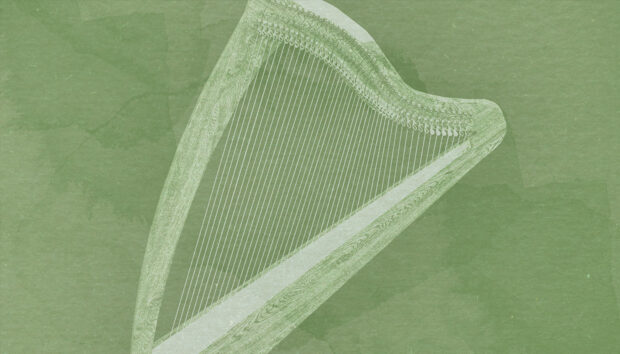作曲家、プロデューサー、エンジニアとして活躍するRafael Anton Irisarri。彼のサウンドは、過去10年間の最も重要とされているアンビエントミュージックの多くに見ることができる。自身の影響力のある楽曲に加え、他にもJulianna Barwick、Leandro Fresco、Steve Hauschildt、Benoît Pioulardなど数多くのアーティストとのコラボレーションを行っている。彼が所有するニューヨークのマスタリングスタジオ Black Knoll Studioは、坂本龍一、Telefon Tel Aviv、Loscil、William Basinski、Eluvium、Grouperまで、エレクトロニカやアンビエントに隣接する音楽の名手たちが発表した作品にクレジットされている。
彼の音楽を一言で言い表すのは簡単ではないが、今までに多くの人が試みてきた。彼の作品は、「ノイズ音やドローンが、モルタルのように深く塗りたくられたテクスチャー」、「美しく荒涼とした」、「変幻自在の暗闇に包まれる」などと様々な表現がされてきたが、2010年の作品と比較するのがベストかもしれない。おそらく、2010年のシングル “Reverie”を “半世紀後に屋根裏部屋から救出されたアンビエント・シンフォニー・レコーディング “と比較するのが最も良い表現ではないか。ラファエルは現代のアンビエントの中でも、よりメランコリックなものに惹かれていると言ってもいいだろう
最新アルバム『Peripeteia』では、メタルやクラシックの世界からの影響を、様々なテクスチャーの分解と再構築のプロセスを通してフィルターにかけている。聖歌隊、ギター、カスタマイズされたKONTAKTに、彼のトレードマークであるオクターブのファズ、独自に拾い集めた音、そして空洞のような残響音を重ね合わせている。
アンビエントのダークアートについての知見を得るため、NIのインストゥルメントとエフェクトを長年愛用している彼に連絡を取ったところインタビューに応じてくれた。アンビエントサウンドの美学、環境から得るインスピレーション、独自のKONTAKTの使い方など、プロセスの詳細を以下で語っている。

あなたにとって、”アンビエントな音”あるいは”アンビエントミュージックに適した音”とは何ですか?
Brian Enoは、1978年に「アンビエント」という言葉を作った。当時、彼は「アンビエントミュージックは、面白くも聴き流せるものでなければならない」と語っていたんだ。当時の初期のアンビエントや実験的なエレクトロニックミュージックがどういう立ち位置であったのか、そして今聴いている音楽がどこにあるのかを考えてみると、そこに様々なアイデアがあると思う。例えば、(多くの人が典型的なアンビエントアルバムと考えている)Enoの『Discreet Music』とTim Heckerの『Virgins』を比較してみて。この2つはサウンド的にはかなり離れているけど、同じエコシステムの中に収まっているんだよ。
私にとって “アンビエント“なサウンドが面白いのは、その時代を超えたクオリティーの高さにあると思うんだ。Brian Eno、Harold Budd、Clusterなど、40年近く前に作られたレコードは、今でも聴くたびに新鮮で面白い音がするよ。それらの作品は全て、何かのストーリーを伝えようとしていた。完璧な音質だったとしても、作品が何も語りかけて来なければ、果たしてそこに意味はあるだろうか?私のお気に入りの作品の中には、技術的には完璧ではないけれども、私が非常に高く評価する美学を持っているものがある。究極的なことを言えば、私にとって良い音は、別の人にとっては恐ろしい音に聞こえるかもしれない。
私の美学は非常に特殊なもので、特に偶発的なもの、壊れた音、エラーに惹かれている。知ってるかもしれないけど、アナログ機器で起こるような素晴らしいアクシデントとは異なり、デジタル技術では、すべてが完璧で安定していることが前提になっている。設計上、正確で均質であることが前提となっているはずの技術を使ってユニークなサウンドを生み出しているのは凄いことだよ。
私にとってアンビエントサウンドとは、特定のツールや技術、プロセスではなく、その音が呼び起こす感覚や、特定の音で何を創造的に実現できるのか、音楽作品の文脈の中でどう使うのか、ライブパフォーマンスにどう組み込むのか、ということの方が重要だと思う。
全てのケースで通用するルーティンがあるとは限りませんが、サウンドをデザインする際には何か特定のステップを踏んでいるのでしょうか?また、プロセスがあるとしたら、どのようなものでしょうか?
私のサウンドデザインのプロセスは、何かのきっかけからインスピレーションを得ることから始まる。数年前、休暇でアイスランドに行ったんだ。アイスランド中を旅していたとき、スナフェルネス半島周辺の古代氷河の氷冠が溶けていくのをたくさん目撃した。地元の人(と科学者)は、この現象は温暖化によって気温が上昇したによるものだと考えていた。
私はこの恐ろしい発見に感化され、すぐに制作を始めたよ。この地域でのフィールドレコーディングから始めたんだ。氷が溶ける音から「媒体の活性化」(フォーリーサウンドのようなもの)を行い、腐食されていく地形の音を収録した。
次のステップで、それをニューヨークのBlack Knoll Studioに持ち帰り、サウンドデザインに取り組み始めたんだ。私はフィールドレコーディングをREAKTORのMetaphysical Functionに取り込む実験をし、それを使って何時間もかけて新しい環境を作り、様々な即興演奏を録音し、サウンドライブラリを作り上げた。結果的にそれが2019年のアルバム「Solastalgia」の素材となったんだ。
作曲を始める前、私は特定のテーマから影響を受け、サウンドを作る。Daisの最新アルバム『Peripeteia』の場合は、”予想外の運勢の変化”というものを考えてサウンドをデザインしたんだ。2019年に全ての曲が作られたと考えると、ちょっと不気味な感じがするけど、あの頃は2020年がこのような急激な変化に満ちているとは知らずに作曲していたね。

サウンドデザインが先で、実際の作曲は別のプロセスなんですか?
アンビエントミュージックの場合、両者は本質的にリンクしているんだ。多くの場合、サウンドデザインのプロセスが作曲の指針となることもあれば、作曲がサウンドデザインの指針となることもある。例えば、William Basinkiの代表作「The Disintegration Loops」。これらの楽曲のサウンドデザインもまた、そのプロセスとアクシデント(訳註:アーティストが古いリールのテープを操作していた際に誤って破壊してしまった件)がなければ生まれなかっただろう。私にとっては彫刻を作ることに似ているんだ。多くの人がそれを再現しようとしたが、 Basinskiが捕らえた、特定の瞬間に起こった数値化できない決定的な要素が欠けている。
Basinskiのように、あなたの音楽にもテープルーピングやそれに関連したテクニックが多用されていますが、あなたの音楽がどのようにして生まれたのか、いつも興味があります。それらがどのように(あるいはどの程度まで)テンポ同期しているのか、あるいはお互いに”上手く作用”しているのか、いつも気になっています
それは作ろうとしている作品の種類によるね。もっと「しっかり作曲された」アンビエントであれば、クリックトラックを用意して、ルーパーを特定のテンポに同期させ、それに沿って演奏しながらモチーフをループさせて行くし。あるいは、何かのサンプルを取ってきてBPMを把握し、それを処理した後にどう変化するか(例えば、Varispeedをかけたり)を考えたりもする。
他にも、もっと不定形な作品の場合は、2つのループの間でランダムに同期させたり同期させなかったりと、1970年代にBrian EnoやRobert Frippプのようなプロデューサーが模索していた初期のテープで行なった実験に近いものがある。初期のアンビエントのレコードのいくつかが非常に面白くて、特別だったのは、ループがランダムに相互作用していたからだね。その文脈を踏まえて、2つのループを延々聴き続けることだって出来るよ(例えば「Music For Airports」のどの楽曲でも)。
アンビエントというジャンルは、素材自体よりもその処理が重視されることが多いです。「The Disintegration Loops」にまつわる伝説は、その最たるものだと思いますが、ご自身の作品においてもそのようなバイアスに共感する所があるのでしょうか?
音のソースは、特定のアイデアをインスパイアするためのものだと思う。私の場合、周りの環境からインスピレーションを得ているけど、弦楽器からもインスピレーションを得る時もある。10代の頃にギターとベースを習っていたんだが、それが今の仕事のやり方に大きく影響しているね。場合によっては、ギターを音源として使用し、その音をギターとは分からなくなるまで加工することもある。フィールドレコーディングやシンセサイザーなどの他の音源についても同じことが言えるよ。自分にとっては、音で何かユニークなものを作り、音で自分がどんな人間で、どんな人物になろうとしているかを表すことの方が大事なんだ。音が喚起する感情や感性は、このプロセスにとって非常に重大であり、それらが何であるかを認識することが欠かせない。言うまでもなく、”汝自身を知れ”という古い格言があるが、まさにその通りだ。”汝の音を知れ”。 自分なりの道を見つけろということだね。
“自分のギターの演奏をエフェクトとアンプを通し、KONTAKTを使ってサンプリングして、S88で鳴らしたんだ。”
そのような音源を加工する際に便利なツールやテクニックがあれば教えてください。
ギターを扱うときはいつも、自分が何をしようとしているのかに応じて、あらゆる種類のエフェクトペダルを使うね。また、例えばチェロの弓を使うなど、実験的なことも行なっている。また、ハードウェアだけですごい音が出てくることもあるので、C音を録音して、それだけをKontaktに取り込んで、その音をシンセのように使うこともある。ちなみにこの考え方はギターに限ったことじゃなく、ほとんど何にでも応用できるんだ。
例えば、Peripeteiaのアルバムには、FM8をソースにして作ったレイヤーがある。同じ手法を利用して、サウンドカードの出力をディストーションやモジュレーションなどのエフェクターに送るんだ。
“2:26頃に入ってきて最後まで流れるリードシンセには、重く処理されたFM8のパッチ(ハードウェアを通したもの、リアンプしたもの、テーピングしたものなど)を使ってる。”
よく使う自作のKONTAKTライブラリはありますか?
自作のライブラリとしては用意していないけど、気に入ったサウンドはいくつかあるよ。スタジオで作った様々なサウンドのサンプルがね。でも制作する時はいつも、過去に作ったサウンドやプリセットは一切使ってないな。全てアルバムごとに特別に作ったもので、ほとんどの場合はイチから作る。制作や学習する上で一番の方法は、自分らしいことをやってみること、実験すること、そして「こう聴こえるべき」という固定概念に囚われないことだと思うんだ。
これからアンビエント音楽を探究しようとしているプロデューサーや、サウンドデザインのテクニックを探究しようとしているプロデューサーに向けて、最後にアドバイスをお願いします。
ひらめきを大事にして欲しい。自分自身に忠実であること。自分に合ったものを作ること。つまり、ある人にはしっくり来る音が、別の人は必ずしも好みの音だとは限らないということなんだ。ネット上にはサンプリングに関する多くの素晴らしいヒントがあるけど、それで面白いと思えるサウンドを(自分にとって、自分の状況に合ったユニークで具体的である何か特別な物を)作れなければ意味がない。
多くの場合、我々は「あれが有ればはるかに素晴らしいものを作れるのに」といった思考プロセスに気を取られてしまう。でも、既に自分が持っているものだけで何か素晴らしい音が作れると思うんだよね。取り組んでいる作品の文脈の中で、素晴らしい音にする方法を思い付くために時間をかける必要があるだけなんだよ。それには沢山の試行錯誤が必要だ。何時間もかかるけど、最終的にはもっと多くの可能性を秘めた物が出来上がるかもしれない。まずはその可能性に賭けてみることだ。

Rafael Anton Irisarriの最新プロジェクトの情報をチェックするにはTwitteやInstagramを、楽曲を購入するにはBandcamp、そしてBlack Knollのマスタリングサービスについてはblackknollstudio.comチェックできます。