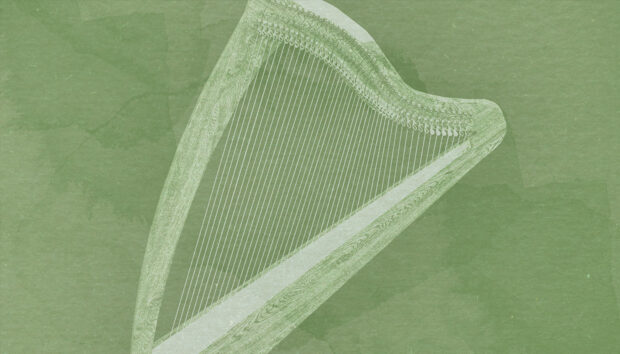Major SevenがMASCHINE+とMASSIVE、PRISM、そして内臓のDrum Synth使ってゼロからビートを作り上げる様子を見てみましょう。以下のインタビューでは、彼のビートメイクのアプローチやトッププロデューサーである彼からのアドバイスを紹介しています。
ヒップホップ・プロデューサー、Omar “Major Seven” Walkerが故郷アトランタの影響を受けていることは間違いないが、彼のシネマチックで予測不可能な展開の楽曲には、音数が少なく、陰気とも言えるアトランタの典型的なトラップ・ミュージックにはない壮大さや音楽的ディテールがある。少年時代には、Kanye Westの『The College Graduate』のエモーショナルなソウルとゴスペルのサンプリングや、Dr. Dreが手掛けたEminemの衝撃的なヒット曲群、そしてJay-ZやTupacらのインスピレーションに満ちた力強いリリシズムに多大な影響を受けたMajor Sevenは、いつしかストーリー性のある楽曲づくりを目指してトラック制作を始めていた。「色んな思い出や感情がこの音楽と結びついてる」と、彼は言う。「俺にとっては単にビートを作る、ってことじゃなくて、どうやって感情を切り取ってトラックに落とし込めるか、なんだ」
最初に彼がメインストリームで注目を集めたのは、2013年後半リリースのRick RossとJay-Zのヒット曲、“The Devil Is a Lie”であった。迫力のあるドラムロールや、鋭いスネア、マーチング・バンド並のキックが特徴的な彼のこのビートは、Gene Williamsの1970年のソウルバラード“Don’t Let Your Love Fade Away”を巧みにサンプリングしている。「(Quentin Tarantinoの映画)『 Django Unchained』を見ていたときにこの曲を聞いて、最初からすぐにサンプリングしたいと思った。曲のあちこちでサンプリングしたら最高だなと思える瞬間があって、ウーとかアーとか歌声も入ってて。特にブリッジで展開がガラッと変わるところ、あの“バン、バン、バーン”っていうところを聞いたとき、すぐに全貌が見えた。すぐに2 Chainz、Rick Ross、Jay-Zとかがラップしてるのがイメージできて、あと西部劇のフィーリングもあった。その勢いをトラックに注入しようと制作したんだ。作るときは最初にビジョンを持つことは大事だと思う。たいてい、実際に最初に思い描いた通りになるからね」
同曲でヒットを飛ばしたとき、彼はすでに数年ビートメイカーとして活動していた。“The Devil Is a Lie”を手掛けるまで、数百、あるいは数千ものトラックを制作したかもしれないと彼は言う。以降、彼はFuture(『HNDRXX』収録の “Fresh Air”、”Neva Missa Lost”、Rihannaとの “Selfish “など)、T-Pain、Dave East、DJ Khaled、DJ Snakeらとの制作を経験していき、着実にキャリアを築いてきた。そしてその間、彼はNIのMASCHINEとKONTAKTのサンプル・ライブラリを活用し、珠玉のサウンドで破壊力抜群のループを効率良く生み出してきた。
「MASCHINEをLogic Pro X内で、ドラムの打ち込みをコントロールするマルチティンバー・インストゥルメントとして使っている」と彼は説明する。「MASCHINEのソフトウェアで直接クリックして演奏を微調整したりもする。でもハードウェアのほうが実際に演奏している感覚で制作ができるから好きだ。MASCHINE Mk3には、ノートリピート機能や、サンプルの開始点と終了点をノブで設定できるサンプラーなど、良い機能がたくさん搭載されている。これを使えば、手を動かすのが楽しくなってくるね。料理をしている感覚で楽曲づくりができるんだ。わかるかな?」
「MASCHINEを使うのが自分にとってすでにデフォルトになってる。お気に入りのドラムネタも保存してあるしね」と彼は言う。「だから他の機材よりも素早く音を調整したり、アイディアを試したりできる。Native Instrumentsの機能で特にドラムによく使うのがTransient Masterなんだ。アタックとリリースを細かく調整できて、スネアのアタックを強くしたり、短い小刻みな音に変えたりできる。MASCHINEのサンプラーが好きなんだけど、たいてい最初のグループの16スロットを全部使い切っちゃうから、他に使いたい音があるときはLogicのサンプラーも使って音を取り込んでる。Logicのサンプラーもだいぶ改善されてきたから、両方を行ったり来たりすることが多い」

彼はKONTAKTの定番系の音源ライブラリからメロディー要素やスタブを抜き、音を調整したりエフェクトをかけて使うのも好きだと彼は語る。「New York Concert Grand Pianoというのをよく使ってる。ピアノといったら自分はあれを使うね。あと、Scarbee Vintage KeysのRhodesとか。80sレトロなAnalog Dreamsも最高だね」
ブラジル産バイレファンキを使ったFutureの“Fresh Air”や、Billy Boyoのアイコニックなストーナー・アンセム“One Spliff A Day”を拝借したDJ Khaledのモンスター級レゲエ・ヒップホップ、“Holy Mountain”など、Major Sevenの代表曲においてサンプリングが重要な役割を果たしていることは言うまでもない。「すべての曲で、何かしらサンプリングはしてる」と彼は言う。「常にループをチョップして、リアレンジして、エフェクトかけて全く別のものにしたりしている。曲をサンプリングしていなくても、声ネタとかドラムネタとか何かしらをサンプラーを通して入れてるよ。」VSTインストゥルメントで作られたものさえも、オーディオとして書き出し、それをサンプリングし直し、ピッチを変えてトラックのムードに合わせる、といったことをするという。「サンプリングはヒップホップというアートの一部なんだ」
今回、Major Sevenに新しいスタンドアローン型MASCHINE+を使って、パソコンなしでイチからビートを作ってもらい、そのプロセスを動画に収めた。彼にとって初めての体験であったが、MASCHINEやKONTAKTでお馴染みのインターフェイスのデザインやメニューの仕組みを採用しているため、彼はすぐにプリセットやサンプルメニューを操作することができていた。「MASCHINE+の良いところは、目の前のこれひとつに集中できること」と彼は言う。「楽しいプロセスだった。ボックスで直接アレンジしたりマクロコントロールを調整するのが簡単で、プリセット郡をじっくり確認できたし新しい発見もあった。普段と違う環境で制作したことで、普段だったらやらなかったような特殊なことにも挑戦できたよ」

R&Bに影響を受けたポップバラードをFutureに提供したり、Jodeciの官能的なサウンドをベースにした“Alone”をハーレム出身のハードコアラッパーDave Eastに提供するなど、これまでの活動においてMajor Sevenは型にはまらないことをやってきた。彼のトラックは起承転結のあるひとつの物語となっており、じっくり聴き込まないと気づかないディテールに溢れている。そんな彼に、楽曲をよりシネマチックにするためのアドバイスをきいてみた。「スケールのでかいサウンドにしたいなら、アレンジに気を配るべき」と彼は答える。「曲のなかにちょっと特殊な瞬間を入れるというか…。ちょっとした展開とかに時間をかけてみる。例えば複数のドラムフィルを重ねて、それぞれ別々のエフェクト、パンニングがかかってるとか。そういうことが効果的だったりする。すべては、最初にビッグなアイディア、ビッグなビジョンがあることが大事だ!そして、そのアイディアを実現するためのツールがあるかどうか。自分に投資することも大事だ。音源、ソフトウェア、ハードウェアに投資して、創作に打ち込めるようにしておかないといけない」
「よく、ビートメイカーという意味でプロデューサーという言葉が使われているけど、自分にとっては、スタジオで何足ものわらじが履ける人のことを言う」と彼は続ける。「ある程度エンジニアもできないといけないと思うし、ヴォーカル・アレンジも、ビートメイクも、ソングライティングも…プロデューサーを目指すなら、そういったスキルはすべて身につけるべきだ。特に、コミュニケーション・スキル。プロデューサーの役目はただビートを作ることじゃなくて、明確なビジョンを持つことだ。アーティストが求めていることや、秘められたポテンシャルを察知して、それをはっきりとコミュニケーションしないといけない。自分の好みで考えてはだめだ、その曲にとってベストなことを考えないといけない。そして、出会う人、あらゆる物事から学び続ける。実際にやることで何よりも覚えるから、現場での体験を重ねて慣れていくしかない。他に近道なんてないよ。失敗はするだろうし、時間はかかるけど失敗から学んでいくしかない。最初に作った1000曲はすべてゴミかもしれないが、毎回意識して改善できるポイントを明らかにしていって、しっかり耳で聴いていれば、どんどんと上手くなっていくんだ」