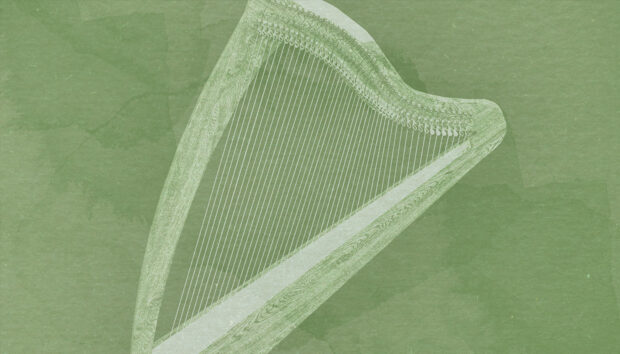Ben Bazzazazianについて語るとき、プロデューサーとしての彼の幅を単に“広い”と形容するだけでは物足りない。Netflixのドイツ語ヒットドラマ「スカイラインズ -危険なビジネス-」のビート制作、ドイツのラップ界が誇るスーパースターHaftbefehlのプロデュース、Rammsteinのスタジオアシスタントなど、Ben Bazzazianはケルンを拠点にあらゆる分野の仕事を手掛けている。彼が他のプロデューサーと一線を画しているのは、ユニークなサウンドと、そのユニークぶりに匹敵する型破りなテクニックだ。
スタジオオタクにしてサウンドデザインのスペシャリストでもあるKabukiがBazzasianのもとを訪れた今回のインタビューでは、スタジオでの習慣、ディストーションで図太い808のキックを生み出すテクニック、そしてNetflixとの仕事について話を聞くことができた。

Benは音楽制作の業界で何年もかけて特別な地位を築きあげてきましたよね。スタジオに行くときは、どんなことを目標にしているんですか?
自分の音楽には個性的であってほしいと思っています。すでに聞いたことのある音にはしたくないので、自分の音を出すことが絶対に最優先です。
例えばシンセサイザーのプリセットを使うと、それはそれでいい音がするけど、まったく同じものを使ったことのある人が20,000人いるかもしれないでしょう。それだと、つまらない。
みんなが真似したがるビートって常にありますよね。「Mask Off」が出たあとは、フルートの曲ばかりを耳にしました。
ですよね。そういうのを僕はいつも避けるようにしてきました。他のみんなを批判しているわけじゃないですよ。そうじゃなくて、僕と同じように考えている人はたくさんいます。僕にとっては、自分の音を出すことが、何よりも大切にしていた決まりです。例えばシンセサイザーのプリセットを使うと、それはそれでいい音がするけど、まったく同じものを使ったことのある人が20,000人いるかもしれないでしょう。それだと、つまらない。その音が違っていてほしいんです。僕は、原形がわからなくなるまでプリセットを極端にいじることもあります。でも、元の音が何だったのか人に知られたくないわけではないんです。そういうことを隠し事にしていない。Haftbefehlのアルバム「Russian Roulette」で「Ich Rolle Mit Meim Besten」という曲があって、その曲では歪んだ808の音を使っています。どうやって作ったのか率直に聞かれたことがあったので、教えてあげましたよ。「808を3つ積み重なっているんだ」って(笑)。だから、秘密にしているわけではなくて、単に自分のやり方で違うことをやりたいだけなんです。シンセサイザーで音をいじってもいいし、バーチャル・インストゥルメントを使ってもいいし、エフェクトペダルを使ってもいい。個性的な音であれば何でもいいんです。
過程が大事ってことが多いってことですよね。「成立しなくなるまで、どれだけやれるかやってみよう」っていうか。
そうやって、やりすぎちゃうこともありますね。以前は実験的なことに今ほど積極的ではなかったと思います。最近だと、色々なアプローチを試してみたいと思っています。例えば、曲のアレンジ。色んなことを試し続けています。実際にやってみないとわからないこともありますからね。そういうことを面倒に思っていたらダメです。僕は1曲に対して5種類以上のリミックスを作ることもあります。そうすれば、どれが一番いいのか簡単にわかりますから。
実験することを恐れず、自分自身にチャレンジすることが必要なんですね。
ポップミュージックのアレンジに秘訣なんてありません。これまでにアメリカで1位になった曲を3000曲集めて、その構造を調べることは簡単にできます。でも、みんながその公式だけに従っていたら超つまらないですよね。
そうしていたら、自分の表現なんて見つかるわけがない。
ですね。音楽的に自分を表現する方法を見つけることが、最も重要です。例えば、Native Instrumentsで利用できるライブラリはどれも良いものばかりだから、最初に使った人はそのまま使えてラッキーですよ。でも、そのあとに続く人たちは、同じ音にならないように何かを変えないといけない。僕がビートを作り始めた頃は、TimbalandやThe Neptunesみたいな人たちがいて、この人の音だってすぐにわかる曲を作っていました。自分の音が他と比べて際立っていて、一個人としての自分に直結していたら最高だと思います。それが常に僕の目標でしたね。
初めてBenのビートを聞いたとき、重厚なドラムの音が印象的でした。いつもドラムをレイヤーにしている気がするんですけど、それはパンクをやっていた経歴と関係があるんでしょうか?
そのとおりです。あと、僕の聴覚障害も関係しています(笑)。ある種の音楽をやるときは、あの迫力が必要なんですよ。そこでドラムが、大きな役割は果たすわけです。ドラムを歪ませることが、カギですね。

以前はプラグインのCulture Vultureを使っていましたが、今も使いますか?
ディストーションが大好きな僕にとって、Culture Vultureは理想のプラグインです。もちろん他にも良い音を出すディストーションはありますよ。Decimortは、僕のドラムサウンドで大きな役割を果たしていると思います。
音が歪んでも威力と存在感のあるドラムにするには、どうしたらいいんでしょうか? 特別なテクニックはありますか?
僕はいつもディストーションをインサートで単発の音にかけています。キックとかスネアですね。それから、ドラムの音をバスにまとめます。Culture Vultureみたいな真空管のオーバードライブを使うのが好きですね。Summingのプラグインも、僕のドラムサウンドにとって大切です。違うコンソールから仮想チャンネル経由で音声信号を送って、もう一度そこで音に色付けすることができるから。
あの独特のドラムサウンドに加えて、パーカッションにもハッキリとしたグルーヴをつけていますよね。クオンタイズは使っていますか? それとも自分でひとつひとつドラムの音を配置しているんでしょうか?
両方です。例えば、僕はいつもThe Neptunesのグルーヴをすごく特別に感じているんですけど、The Neptunesってスネアとキックドラムに結構きつくクオンタイズをかけるのに、ハイハットはかなり緩めのままにしているんですよ。僕のやり方と必ずしも同じってわけじゃないんですけど、そのコントラストがすごく大切なんです。グルーヴとスイングの比率をどうすべきかについては、本当に悩まされますね。たとえ、全部が16分音符でクオンタイズされていても、かっこよく聞こえればいいんです。僕は、クオンタイズのテンプレートが自動で読み込まれるようにしています。MPC、Emulator、OberheimのDMXとか、何でもありますよ。ほとんどの場合、MPC 3000のクオンタイズを52%に設定して16分音符でかけています。全部を自分で手打ちして、クオンタイズをかけないときもありますね。
「スカイラインズ -危険なビジネス-」について話を聞かせてください。音楽スタジオのシーンのリアルさに驚きました。ビットクラッシャーをスネアに使うシーンも、その1つです。そういうことについて相談を受けることはありましたか?
ビットクラッシャーのアイデアは僕が考えました。そういうシーンで僕ならどんなセリフを言うのかって、制作総指揮を担当していたDennis Schanzから事前に聞かれましたよ。僕は材料になるものを提供しただけです。
Benの曲「Skyline Glänzt」はシリーズの中で重要な役割を果たしていますが、この曲はMASCHINEでライブパフォーマンスするために作られたように聞こえるんですよ。制作中からすでにそのことを念頭に置いていたんですか?
いや、ビートは事前にできていて、番組に向けて特別に作ったわけじゃないんです。注文は、シリーズのみんなが夢中になるような盛り上がる曲がほしいというものでした。このビートがここまでうまくハマったのは、今思えば、嬉しい偶然でしたね。
他のアーティストとのコラボレーションについて教えてください。
大抵の場合、僕は他のアーティストのプロデューサーをしています。いい感じなので楽しんでいますよ。あるとき、それでは満足がいかなくなることがあって、それからFarhotと仲良くなって一緒に制作することにしたんです。それが、Die Achseの誕生でした。これまでに「Angry German」と「Hooligan」っていう2枚のEPをリリースしていて、現在はファーストアルバムの制作中で、今年の後半には出てほしいと思っています。
今も、他のアーティストのプロデュースはやっています。例えば去年だと、RammsteinのTill Lindemannの曲「Mathematik」をプロデュースしました。Haftbefehlを起用したんですよ。Till LindemannやOlsen Involtiniとやったスタジオセッションはとても楽しかったです。当分、忘れることはないでしょうね。Olsen InvoltiniがRammsteinの今回のアルバムをプロデュースしていたとき、数曲の打ち込みをやってみないかって声をかけてくれたんです。もちろん、断れませんでしたよ。手がけた3曲のうち、1曲はアルバム「Ausländer」に収録されました。僕は今、この春にリリースされる予定のHaftbefehlの新しいアルバムに取り組んでいます。
アウトボードの機材や音源を楽曲に組み込むことが多いですよね。何かしら決まったやり方はあるんでしょうか?
制作で何か足りないものがあると感じたときは、外付けのキーボードやエフェクトペダルをよく使います。でも、アナログ支持者というわけじゃないですよ。あの手の議論はつまらないと思います。つまるところ、音源は何でもいいんですよ。音がよければ、うまくいきますからね。アウトボード機材の音は、アナログ支持者にとって魅力的であることが多いです。それが何なのかハッキリとはわかりませんが、何か特別なものがあるんでしょうね。ソフトウェアのツールもよくいじりますけど、実際のハードウェアを使ったほうが楽しいです。だから、これ(MASCHINEを指差しながら)が最高なんです。両方を兼ね備えていますから。

普段だと、まず曲の土台を作ってから、そのあとに細かい部分を意識するようにしているんでしょうか?
基本的にはそうですけど、音楽制作と音の調整はきっちりと切り離せないことが多いです。でも、ミキシングや音の調整とか、音作りなんかを早い段階からやると、集中力が切れることがわかっているので、曲を簡単に作ってから細かい部分に取り組むようにしています。長年かけて自分を鍛えたので、曲の雰囲気が良いときは全体を変えすぎないように自分を抑制できるようになりました。
細かい部分が相互に作用して、そこで全体像ができあがるのが大切ですよね。
同感です。音量を適切に調整すればいいだけのときもありますよね。自分の曲をミックスやマスタリングに出すときは、すべてが整っている状態にして、聞こえてほしい感じの音にしています。それからエンジニアが残りの20%をいろいろと調整して、いくつか周波数を削ったり、リバーブのアルゴリズムを加えたりします。一緒に仕事をしているエンジニアは、僕よりボーカル処理が上手です。僕はこういう仕事の配分も好きですね。
プロデューサーとしての役割を果たすうえで、信念にしているものはありますか?
自分でできるからといって、色々とやってしまうのは愚行だと思います。他の人の楽曲であるなら、自分でできるからといってスネアを入れ替える必要はありません。かっこいいものであるなら、そのままにしておいていいです。それがアップルループでも、かっこよければ。僕が音に手をつけるのは、そうする意味がある場合です。単にKORGのMS-20があるからといって、常に使わなければいけないわけじゃありません。そこは、自分の主義を持ち込むところじゃないです。アナログ機材と同じくらいいい音だ、アナログ機材は必要ないって言って、コンピューターで全部やる人がいますよね。それは大丈夫なんですけど、アナログでもデジタルでも、実用的な道具を軽視してはいけないと思います。
僕が音に手をつけるのは、そうする意味がある場合です。単にKORGのMS-20があるからといって、常に使わなければいけないわけじゃありません。
最終的に僕らが耳にするのは、何を使ったかではなく、アーティストが刺激を受けているかどうかですからね。
同感です。それに、大事なことですよね、感覚って。デジタルのシンセサイザーでも自分の求める雰囲気が得られるなら、それでいいんです。